彼女の事情と彼氏の想い (2)
絶対に、試合はするな。
・・・しつこいくらいに念を押されて、何度も「わかりました」と返事をさせられて。
翌朝、蘭は団体戦の会場にいた。
昨日新一に連れて行かれた病院で、診断結果はやはり捻挫。
骨に異常はなかったようだが、かなり熱をもっており(・・・そしてその理由は、捻ってからすぐに治療をせず、無理をして歩いていたせいだ、と医者に言われ、あとから新一こっぴどく叱られてしまったのだが・・・)、腫れもあった。
治療してもらい、とりあえず一晩冷やしたおかげで、何とか朝には腫れは引いたのだが・・・やはり、試合に出るのは難しいようだった。
・・・蘭がそう言うと新一は、「まだ諦めてなかったのかよ・・・」と呆れたようにぶつぶつ言っていたが。
ともあれ見た目は何ともなっていないことに、とりあえずほっと胸を撫で下ろす。
これ以上悪化させるわけにはいかないから、と新一がまた抱き上げて連れていこうとするのを、「そんなことして試合場に行ったら、怪我してるってみんなにばれちゃうじゃない!」と、必死に抵抗し(・・・本音はもちろん、人前でこれ以上そんな恥ずかしいことをされたくなかったからなのだが)、妥協案としてタクシーで会場に乗り付ける、という学生としてちょっとそれはどうだろう、という方法で移動した。
・・・その姿を見た帝丹空手部の生徒たちに、「どうかしたの?」「何かあったの?」と興味津々で詰め寄られ、「何でもないよ!ちょっと寝坊しちゃったから・・・」と笑って誤魔化した。
「・・・観客席で、見てるからな」
なおも心配そうな顔はしていたが、部員でもない新一がいつまでも一緒にいるのは不自然なので・・・最後にしっかり念押しをしておいて、新一は一般の観客たちと一緒に2階の観客席に向かった。
新一の言った「見ている」は、当然、「蘭が試合に出ないように見張っている」という意味なのだが、周りにいた部員たちには本当の意味までは伝わっていない。
なので、新一の後姿にむかって、
「工藤君、大将の蘭まで回す前に私たちで勝負つけちゃうから、蘭の活躍は見られないかもよ!」
「ちゃんと他の選手も応援してよね!」
・・・などと声をかけていた。
「・・・言ったな? ぜってー蘭まで回すなよ?」
冗談めかして答えた新一の言葉は・・・彼の、嘘偽りない本心であろう。
その姿を内心で苦笑しつつ見送ってから、蘭は他の選手たちと一緒に更衣室で道着に着替え、大会の会場となっている体育館へと入っていった。
帝丹高校は優勝候補。
その選手たちの登場とあって、蘭たちが入ると会場中にはぴりりとした緊張が走り、そこかしこからざわめきが上がっていた。
特に昨年2年生にして都大会で優勝している蘭には、すべての学校の選手たちが注目しており、周囲からかなりの視線が集まっている。
それを痛いほどに感じながらも、蘭は平静を装いつつ、部員たちと笑顔で会話を交わした。・・・もちろん、足の痛みなどおくびにも出さず。
やがて開会式が始まり、各チームが自分たちの試合が行われるブロックへと散らばってゆく。
蘭もチームメイトたちと一緒に、帝丹高校が振り分けられたいるAブロックの試合場へと移動した。
大会が始まる。
体育館のそこらじゅうから、気合の入った掛け声が大きく響いてきて、会場はすぐに熱気に包まれた。
・・・そんな中、優勝候補の帝丹高校は、順調にトーナメントを勝ち上がっていた。
帝丹で強いのは、蘭だけではない。
蘭と一緒に練習を積んできたメンバーたちは、それぞれが注目を浴びるに十分な実力を備えた選手たちばかり。だからこそ団体戦でも優勝候補と目されるのである。
・・・蘭に回す前に勝負つけちゃうから、と言っていた部員の言葉は、半分は冗談であるものの、もう半分は彼女たちの自信の現れでもあった。
「この調子なら、ほんとに蘭の出番、ないかもね!」
副部長兼副将の亜矢が、タオルで汗を拭いつつ上機嫌にそう言った。
準決勝も、蘭の出番はなかった。・・・途中まで手に汗握る試合展開だったのだが、副将の亜矢が相手チームの副将、大将を続けざまに撃破して、決勝進出を決めたのだ。
「決勝くらい、わたしの出番も残しておいてよね!」
チームメイトの活躍をねぎらいながら、冗談めかしてそんな言葉を口にする。・・・もちろん本心は、違うところにあったのだけれど。
「やあよ。工藤君に、絶対に蘭まで回すなって言われてるんだから!」
「そうそう! 蘭は来週の個人戦もあるんだし、今回は最後まで休んどいて!」
「全国大会まで大将温存なんて、カッコいいよね!」
何も知らない選手たちは、無邪気にそんな会話を交わし、はしゃいでいる。
その様子を苦笑して見つめながら・・・蘭は、やはり怪我のことを隠しておいてよかったのだと思った。
後に大将の蘭が控えていると思うからこそ、彼女たちは気負わずに思いっきり戦うことができる。
これが本当に、蘭まで回すことができない状況なのだと知っていたら、きっと余計な緊張で、実力のすべてが出せなくなってしまっていたかもしれない。
「じゃ、今日はラストまで休ませてもらおうかな」
口調は冗談、内心は本気でそう言ってから・・・蘭はちらりと、観客席のほうに視線を送った。
2階席の後ろのほうに、小さく新一の姿を見つける。
遠すぎて表情までは見えないけれど、こちらを心配そうに見ているのは間違いないだろう。
(・・・ほんとに、わたしが試合に出ないように・・・最後まで見張ってるつもり?)
事件だ何だといつもならすぐにどこかに行ってしまうくせに、こんな日にはどこにも行こうとしないんだから。
・・・それが、蘭を心配してのことだというのはわかっているので、少し嬉しくも、あるのだけれど。
とにかく、あとは決勝戦だけ。
相手チームは・・・帝丹と並んで優勝候補といわれている、清栄高校。これまでにも練習試合などで何度も対戦しているし、お互いに実力をよく知っているチームだった。
実力は伯仲しているけれど・・・今日のみんなの調子なら、きっと勝てるはず。
他の選手たちが蘭を信頼しているように、蘭も他のチームメイトたちの実力を信頼しているのだ。・・・きっと、有言実行してくれるはず。
やがて、試合開始の合図が聞こえた。
足首の痛みをその表情にはまったく出さず、他の選手と並んで対戦相手と礼を交わす。
そして、先鋒同士の試合が始まった。
※※
清栄高校との対戦は、手に汗握る白熱戦となった。
帝丹の先鋒が一勝すれば、清栄の次鋒がそれを破る。
次鋒同志は引き分け。
続く中堅戦は清栄が勝利を収め、帝丹は副将の亜矢が出ることになった。
「・・・大丈夫。蘭まで回さないわよ。・・・あっちの大将まで私が片付けてくるから」
立ち上がり際、亜矢が蘭の耳元で囁くように言った。
「亜矢・・・?」
「工藤君に恨まれたくないからね。蘭はゆっくり見学してて」
「亜矢、もしかして・・・」
はっとして亜矢の顔を見上げると、彼女はにっと笑ってガッツポーズをしてみせる。
「私だって3年間、あんたと一緒に頑張ってきたんだもん。絶対、全国に連れてってみせるから。・・・見てて!」
それに対して蘭が何か言うよりも早く、亜矢は試合場へと飛び出していった。
(亜矢・・・知ってたんだ・・・)
急に自分が恥ずかしくなった。
大将の自分が怪我をして出場できないと知れば、きっとみんなは動揺してしまって、実力を出し切れなくなってしまうんじゃないか・・・って、勝手にそう思っていたのだけれど。
亜矢はちゃんとそれを知っていて、そしてだからこそ蘭のために、頑張ってくれていたのだ。
そう思ったら、ちょっと自分が情けなくて、けれど亜矢の気持ちが嬉しくて。
(亜矢、頑張って・・・!)
相手の中堅と拳を交える亜矢の背中に、蘭は心の中で強く呼びかけていた。
そんな蘭の声が届いたのか。絶対に蘭まで回すものかという気迫が拳に乗り移ったのか。
亜矢は相手の中堅、副将を、続けざまに破った。
「よーし、亜矢! ついでに大将もやっつけちゃって!」
チームメイトの声援に、亜矢はやっぱりガッツポーズで応える。
「まかせといて!」
だが、その言葉とは裏腹に、時間いっぱい使って清栄高校という強敵の選手を2人も破っている亜矢の顔には、疲労の影が見えていた。
汗もすごいし、息もけっこうあがっている。
「亜矢、無理しないで!」
思わずかけた蘭の言葉に、亜矢は「心配いらないから!」と頼もしく答えて、大将戦へと向かっていった。
そして試合開始の合図。
亜矢と清栄の大将が、拳を合わせる。
お互いの気迫のこもった掛け声が、場内にこだまする。
・・・蘭は試合の行方を見つめながら、ぎゅっと両手を握り合わせていた。
こんなに頑張っている亜矢と一緒に、そしてみんなと一緒に、インターハイに行きたい。
でも、今日のわたしには、そのためにできることは何もないから・・・だから、亜矢、頑張って・・・!
けれど。
亜矢の頑張りも、蘭の願いもあと一歩届かず。・・・3人抜きを達成することは、できなかった。
「帝丹高校、大将、前へ!」
審判の声が大きく響く。
決勝戦なので、会場中の観客がこの試合の行方を見つめていた。
・・・いよいよ、大将同士の勝負だと、場内が大きくどよめく中。
蘭は、すっくと立ち上がった。
視界の隅に、こちらを見ているであろう新一の姿が小さく写る。
(・・・ごめん、新一・・・)
あんなに約束したけれど。・・・ここで棄権なんて、絶対にできない。
「・・・蘭・・・棄権、しよう? その足じゃ、無理よ・・・」
泣きそうな顔で、亜矢がそう口にする。
絶対に蘭まで回すものかと思っていたのに、それを果たせなかったから・・・責任を感じているのだろう。
蘭はそんな亜矢の肩をぽんと叩くと、軽く片目をつぶって見せた。
「・・・最後の最後まで亜矢たちが休ませてくれたんだもん。大丈夫」
本当は、歩くごとに足首が悲鳴を上げていたけれど。
でも、そんなことはもう、どうでもよかった。
ただ、みんなのために。
ここまで頑張ってくれたみんなの・・・亜矢のために、やらなきゃいけないと、そう、思った。
※※
清栄高校の大将は、個人戦でも蘭のライバルと言われている選手だった。
当然、優勝候補にもあげられている強敵だ。
蘭もこれまで、何度も対戦してきた。・・・だが、これまで一度も負けたことはない。
きっと彼女は、この高校生最後の大会で、今度こそ蘭に勝ってみせると意気込んでいることだろう。・・・その気迫が、絶対に蘭まで回すものかと決意していた亜矢の気迫をも上回り、蘭をこの大将戦まで引きずり出すことに成功したのだ。
両校の声援が会場中から聞こえる中、試合前の礼を交わした二人は中央へと躍り出る。
左足は、もちろん痛い。
でも、負けたくなかった。
これは決勝戦。しかも大将戦。
どうせもう後はないのだから・・・だからもう、怪我のことは考えないで、精一杯、戦ってみせる。
そして亜矢と、みんなと一緒に、インターハイに行くんだ。
・・・無心で、戦っていた。
怪我のことは忘れていた。
考えることなく身体が動いていた。
・・・そして気づいたとき。
蘭は、試合場に、崩れ落ちていた。
「・・・蘭!!」
蘭の名前を叫び、誰よりも早く駆け寄ってきてくれたのは。・・・やっぱり、新一だった。
「・・・勝ったよ、新一・・・」
「勝ったよじゃねーよ。このバカ!」
自分を抱き起こす新一の腕にもたれかかり、ふふ、と笑った蘭に向かって、新一は思いっきり顔を顰めてみせた。
「・・・わりー。こいつ、連れてくから・・・あとよろしくな」
一歩遅れて駆け寄ってきていた亜矢たちに向かってそう言うと、新一は蘭を抱き上げる。
・・・だから、人前でそんな風に運ばれるのは恥ずかしいから嫌だって、昨日から言ってるのに・・・ぜんぜん、人の言うことを聞いてくれないんだから。
そうは思ったものの、今日だけは仕方ないかもしれない。
だって新一の言うことを聞かずに、無理して試合にでちゃったから、こんなことになったんだし。
「蘭!・・・ごめんね、無理させて・・・でも、ありがとう。これで、みんなで全国に行けるね!」
新一に抱き上げられた蘭に、亜矢が駆け寄ってその手を取った。
「亜矢・・・わたしこそ、ごめんね。わたしが怪我しちゃったせいで、亜矢には負担をかけちゃったね・・・」
「ううん!蘭に回すもんか、って思ったら、今日は実力以上に頑張れた気がするもん!蘭にはお礼を言いたいくらいよ?」
どこまで本音なのかはわからないが、亜矢は笑ってそう言ってくれた。・・・そして新一に対しては、「ごめんね、結局蘭を試合に出させちゃって・・・」と本当にすまなさそうに誤った。
新一は「オメーらのせいじゃねーよ」と苦笑してみせて、そして亜矢たちを残して会場をあとにする。
もともと会場中の観客に注目されていた試合の直後である。
蘭を抱き上げて連れてゆく新一に対し、なぜか、観客席から大きな拍手と喝采が浴びせられたのだった。
※※
「・・・ねえ」
蘭を背中に負ぶって歩く新一の後頭部に、小さな声で呼びかける。・・・が、返事はなし。
今度はもう少し声を大きくしてみる。
「・・・ねえってば」
「うるせー」
「・・・・・・」
冷たい声でぴしゃりと言われ、蘭は口をつぐんだ。・・・こんなことを、3分おきに繰り返している。
大会が閉会したあとの帰り道。
試合で無理をしてしまったせいで、すっかり歩けなくなってしまった蘭に、医務室で応急処置を施したあと、新一は蘭を背負って帰路についていた。
・・・なぜ昨日のようにお姫様抱っこでないのかといえば、このほうが疲れないというのもあるかもしれないが・・・多分、蘭の顔を見なくてすむからなのではないのか、と、勝手に蘭は思っている。
新一が怒るのも、無理はない。
あれだけ何度も何度も、「絶対に試合には出るな」と念押しされていたというのに・・・そして蘭もそのたびに、「わかった」と答えていたというのに。
蓋を開けてみれば、結局は新一との約束をしっかり破って、無理をして、あげく、こうして迷惑をかけることになってしまったのだから。
だけど・・・例え新一にこうして怒られてしまうことになったのだとしても、あの場で棄権しますだなんて、どうしても言えなかったのだ。
「・・・まだ、怒ってるの?」
「怒ってねーと思ってるのか?」
「・・・思ってない」
「じゃあ聞くな」
・・・取り付くシマもない。
蘭は新一の背中の上で、しゅんと小さくなるしかなかった。
自分が悪いのだから仕方ないのだけれど、こんな風に怒られてしまうと・・・どうしていいのかわからずに、泣きたくなってしまう。
だが、新一の肩につかまっている蘭の右手の上に、新一がこつんと自分の頭を倒してきた。
「・・・って、嘘だよ。もう怒ってねーから」
さっきまでの低い声が嘘のような、穏やかな声。
「新一・・・」
「けど、あんま無茶すんなよな・・・。オメーが試合してる間、どんだけ心配したと思ってんだよ・・・」
ほっとして息をつく蘭に、新一は今度は「怒っている」というよりは「拗ねている」に近い口調で、ぶつぶつとこぼしてきた。
「・・・ごめん」
「よっぽど、試合途中で飛び込んで連れ去ってやろうかと思った」
冗談のように言ってはいるが。・・・意外と、本気でそう思っていたのかもしれない。
それでも・・・最後まで飛び出してくるのを我慢してくれたのは・・・あの時の蘭の気持ちを、わかってくれたから、なんだろうか。
「・・・でも、試合が終わるまで・・・待っててくれたんだ」
「ああ・・・。これが1回戦なら、速攻でやめさせてたけどな」
「なんで1回戦なら止めるのよ」
「・・・オメーなあ。今その足で、もう1回やれって言われて、ちゃんと試合できるのかよ。1回戦で怪我悪化させて、しかも対戦相手に大将が怪我人だってバレてて、それ以上勝ちあがれるわけねーだろ? けど決勝なら・・・もう試合はねえからな」
まったくもって、その通り。・・・まあ、新一の言う通りだからこそ、蘭も怪我のことを考えずに試合をすることができたのだけれど。
「ほんとは、あの試合だって止めたかったんだけどな・・・」
ぽつり、と、今度は独り言のように、新一がつぶやいた。
「新一・・・」
亜矢が負けてしまった時点で、「まずい」と思ったのだと新一はいう。
蘭の性格をわかりすぎるほどわかっている新一だからこそ、あれだけ「試合に出るな」と念押ししていたとはいえ、あの場面で蘭が「棄権します」とは言えないだろうと、わかったのだ・・・と。
だからすぐに、観客席から試合場へと駆け下りた。・・・試合を、やめさせるために。
・・・だが、それができなかったのだという。
「・・・試合前の、オメーのあんな顔見たら、止められねーよ」
首を後に回して、背中の蘭に振り向いて。・・・新一は困ったような照れたような笑い方をする。
蘭はその言葉の意味がわからずに、きょとんと新一の顔を見返して首をかしげた。
「あんな顔って?」
「・・・あんな、真剣な顔。なんつーか、覚悟を決めた顔っていうか・・・その、なんだ・・・」
新一はちょっと口ごもり、振り向いていた顔を戻して前を向く。
おかげで蘭からは、新一の後頭部と首筋しか見えなくなってしまった。
「・・・何よ?」
新一の言いたいことがわからなくて、前を向く新一の顔を覗き込もうと身を乗り出すと、新一は蘭が覗き込んできたのとは逆のほうに、さらに顔を背けた。
・・・そして、さらに小さな声で、呟いた。
「だから、その・・・綺麗だったから・・・」
「えっ?・・・何て言った?」
聞き違いかと思って、問い返す。・・・が、
「・・・もう言わねー」
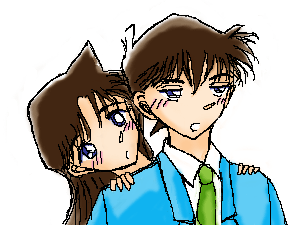
新一はもう、それ以上何も言ってくれなくなってしまった。
おかげで、蘭の耳に届いたその一言が、蘭の聞き違いだったのかどうなのか、確認できない。・・・けれど蘭の目の前にある新一の首筋がほんのりと赤く染まっているのが、はっきりと見て取れて・・・。
蘭は自分の顔も、赤くなってしまったのがわかった。
・・・でも、新一からは蘭の顔は見えないから。
だから、ついでに、ちょっと大胆になってしまおう。
「新一・・・ありがと」
赤く染まった新一の耳元に唇を寄せて囁くと、蘭はそれまで新一の肩に乗せていた両手を回して、新一の首にきゅっと抱きついた。
心配してくれて。
でも、気持ちをわかって、見守ってくれて。
そして・・・本気で、怒ってくれて。
・・・ありがとう。
精一杯の感謝の気持ちを込めた蘭の言葉と行動に、新一はさらに顔を赤くして・・・そして小さく、「バーロ。当たり前だっつーの」と、ぶつぶつと呟いた。
※※
・・・翌週、今度はインターハイ予選の個人戦があったのだが。
優勝候補の筆頭であった帝丹高校の毛利蘭は、棄権した。・・・優勝したのは、蘭の替わりに帝丹高校の代表としてエントリーした、亜矢だった。
大会当日、もう二度と蘭が無茶をしないようにと、新一が蘭を工藤邸に監禁してしまったことは、もちろん他の部員たちには内緒の話である。
maaさんからの頂き物です。
maaさんのサイトの日記発見リクエストに速攻で乗っかっていただきました!
リク内容は「空手で怪我をした蘭ちゃんを本気で心配する新一」でした。
もう、もう、もう!!
本気で心配する新一がツボでツボで・・・vv
っていうか新一蘭ちゃんを監禁してなにしてるの〜(笑)
このお話と一緒にイメージイラストまで頂いてしまいました。
もう、これがラブラブでvv
2重の喜びです。
maaさん、ありがとうございました!