〈12日〉
梅田阪急20:00発の南国交通(株)鹿児島行きバスに乗車する。約12時間の長いバスの旅が始まる。買っていたビールを飲んで眠りに着く。
〈13日〉
予定通り7:30過ぎに天文館のバス停に到着。『さて、これからどうしたものか』と迷っていると、タクシーの運転手に声をかけられる。即決で、港まで運んでもらうことにする。乗船手続きを終えてフェリーに乗り込む。しばらくは甲板でおとなしくしていたのだが、今日は永田の集落までの移動だけということもあり、ゴザを借りこれからの山行の成功を祈念してビールで乾杯となる。
12:46に下船し、半端じゃなく強い日差しの中を、今夜の糧を求めてAコープまで歩く。定番の鍋の具材を買い込み、港へ帰る途中で魚屋さんにより刺身や鍋用の魚を買い求める。気分はもう宴会モードに入いり、うっかり忘れていたが12日に用事があり、遅れて飛行機と高速艇で屋久島にくることになっていた今井さんを迎えにいく。
バスで永田の集落まで移動する。バス停のすぐ横にガソリンスタンドに併設したようにしてあるコンビニ(?)でビール等を買い、バス道路を少し戻り永田川の河口右岸にある松林まで歩く。普段はゲートボール場として使われているらしく、トイレも、水場も、東屋もあるという絶好の場所だ。沖永良部島に沈む夕日を見た後に、東屋の宴会場で、仕入れた食材を前にして3回目になる『山行成功を祈念しての乾杯』をする。
 |
|
 |
|
 |
長い道のりで、やっと屋久島に到着しました。
|
|
沖永良部島に沈む夕日
|
|
今日の宴会場兼寝室です。
|
〈14日〉
5:27、一晩お世話になった東屋を後にして、ポンカン畑の中の道を辿る。6:12、永田歩道の分岐を右に見てさらに林道を進む。6:30林道終点で沢のぼりの装備を整える。軌道跡を少し行くが、すでに跡ではなく自然に帰ってしまっている。沢に降りた方が歩きやすそうなので、早々に沢に降りることにする。幸いなことに水は多くないので順調に溯行ができそうだ。
沢は大きな石で埋まっていて、歩けど歩けどゴーロが続く。一言に大きな石と言っても半端じゃなく、とにかくデカイ。家一軒分もあろうかという石が、次から次から出てくる。中には家どころか豪邸並みの大きさもあるものまで出てくるしまつで、ルートファインディングに悩まされる。水の中には、ハゼの仲間のような魚が泳いでおり、小さな落ち込みを石にへばりついて登る姿も見られる。右に左に、或いは飛び石をしながら溯行していくが、これがとにかく暑い。暑さに堪りかねて、休憩時間に水の中に入って身体を冷やす。溯行図には滝マークが多く書かれていたが、その大半がいわゆる岩間の滝で、断崖にかかる滝はない。いっこうに標高は上がらず、どこまでも続く大石のゴーロの中を時に高巻きを交えながらひたすら歩く。時折、屋久島らしい花崗岩のスラブの側壁を見る。
日もだいぶ傾いてきたが、大石の続く沢床には幕営する適当な場所が見つからない。期待した下の岩屋らしき場所に着いたが、とても大勢が寝れるような所ではなく。15分程度歩いて上流まで偵察にいくが、適当な場所はなく、少し上流に整地すれば何とか6人が横になれるスペースを見つけ、『雨が降れば、ひとたまりもないな』と思いつつも、その場所を今夜のねぐらとした。早速持ち上げたビールと焼酎を沢で冷やしているうちに、焼酎がどこにいったかわからなくなってしまい大ショック。焚き火で服を乾かし、雨が降らないことを祈りつつ、シュラフカバーに潜り込んだ。
〈15日〉
幸いなことに夜間に雨は降らず、ゆっくり寝ることができた。今日は神様のクボを詰めて鹿の沢小屋までの、きつい一日だ。昨日と同じく大石を避ける、或いは乗り越えながら溯行を続ける。約3時間半で上の岩屋に到着する。
右谷に入り、ほぼ1時間で滝がお出迎えしてくれる。この永田川で初めての滝らしい滝で、「これ
!これ!やっぱり、これがなくっちゃ。」と思いながら滝の登りを楽しむ。
その背後には、障子岳の壁が迫っている。壁にしばし見とれた後に溯行を再開する。右岸に注意を払いながら溯行を続けるとなんとなく『沢が流入している地形なのかな?』と思われる場所にたどり着く。神様のクボは「沢幅広く、水量少なく、川床が木々に覆われて」出合っているので、よほど注意をしていないと見過ごしてしまいそうだ。これからが苦労の始まりになろうとは知るよしもなく、半信半疑の状態で神様のクボらしき大石と樹林の中に分け入っていく。
大石の上に屋杉や潅木が生えていて、大石から大石へと登り返しながらという状態となる。時には潅木の幹を渡って隣の石に移り、時には濡れた土と落ち葉で滑る岩を登りという具合である。おまけに大石と潅木で、先は全く分らない。なんとなく左岸よりの方が登り易そうかなということで右へと移動していくが、開けた場所で上流を見てみると、とても上れそうにない。やむなく、右岸よりに上るかということで沢を横断するように移動する。一言で移動と言っても、沢幅が広く、潅木の生えた大石から大石へと乗り移らなければならないので容易ではない。右岸が近づくにつれてチョロチョロとした水音が聞こえてくる。「水の流れのあるところの方が、少しは楽だろう」ということで完全に右岸まで移動する。案の定、水の流れのある場所は少し溯行が楽になる。やがて沢床を覆っていた潅木も無くなり、しばらくは快適な溯行となる。
頭上に稜線が見えてきて、もうしばらくの辛抱だなと気楽に考えていたが、しかし永田川はそんなに甘くなかった。最後に屋久島名物の石楠花が密生した斜面の藪こぎという手で、我々を歓迎してくれたのだ。石楠花の下を、枯れた枝を折って空間を確保し、這いずるようにしながら身体を引き上げていく。腰が強く細い枝がザックに引っかかり、疲れた身体から体力を奪い取っていく。悪戦苦闘の末、左岸よりに石楠花の林の切れた場所を見つけて退避する。
後からから付いて来るメンバーを待っている間に、4m程先の石楠花の中にヤクザルがいるのを見つける。あまりの近さに、襲われた時に備えて、手の届くところにあった石をそっと掴み取る。しばらく睨み合いを続けるが、徐々にメンバーも集合してきて多勢となった我々に、ヤクザルも負けを感じたようで赤い尻を見せて対岸の方へと移動してくれた。
ここからは、石楠花は無くなったものの笹に覆われた斜面がコルまで続いている。密集した笹に乗った足が滑るので、笹を掴んで腕力で身体を引き上げないといけない。斜面をよくよく観察して見ると、笹の斜面に道跡のような線が見て取れる。その線上に移動してみると、雨の流水でその場所は土が無いために、笹が密集して生えていないようだった。やがて斜面の傾斜も落ちて、夕暮れの迫るコルにバテバテ状態で到着する。
疲れ切った顔で全員がコル集合した時には、コルはガスに包まれ、そして薄暗くなっていた。しばらく休憩をして、ザックからヘッドランプを取り出し、鹿の沢小屋を目指して下ることにする。
暗くなった道をヘッドランプの光を頼りに進むが、当然ながらピッチが上がらない。道が正しいのか、間違っているのかすら分らないままに、ひたすら下る。左右から笹が覆った道を歩いていると、ズボンという感じで突然胸まで落ち込む。道の横が溝になっていてその溝にはまり込んだようだ。雨の多い屋久島らしい道だなと関心する。疲れきって途中で何度もビバークをしようかとの思いにかられるが適当な場所も無く、励ましあいながらさらに下降を続ける。
悲壮感すら漂い始めた21:40、突然目の前に小屋の姿が現れる。夜も遅いので、小屋に入るのを遠慮して小屋前にテントを張らせてもらい、簡単な食事をした後に寝袋に入った。神様のコルに入ってから苦労の連続で、まったくもって強烈な一日だった。
〈16日〉
昨日が、厳しく遅くまでの行動だったので、朝はのんびりとして10時過ぎに小屋を出発した。
昨夜、暗闇の中を下ってきた永田岳への道をゆっくりと登る。朝がゆっくりだったせいか、以外にも昨日の疲れは残っていない。1時間程で永田岳頂上と宮野浦岳方面の分岐に着く。『折角だから、永田岳の頂上を踏んでおこう!』ということで、ザックを置いて頂上を目指す。少し上り、鎖場を登って、岩の間をすり抜けた所が頂上だった。生憎、視界が悪くて周囲の景色を堪能するという訳にはいかなかった。早々に頂上から降りて宮野浦岳を目指す。起伏が比較的少ない笹の道をのんびりと進む。ガスが切れ、周辺の景色も見えはじめてきて、いかにも「屋久島の登山道」という感じの道を1時間程で焼野三叉路に着く。一息入れた後に、宮野浦岳の頂上に続く木道の階段を上る。
さすがに、足に疲れが出てくるが全員元気に頂上に到着。頂上に居合わせた他の登山者と記念写真を撮ったり撮られたりしてひと時を過ごし、今日の目的地の石塚小屋を目指して頂上を跡にした。草の中に点在する大岩の形に関心したりしながら歩いてる内に、やがて投石湿原に到着。
そして、さらにしばらく歩いて花之江河に至る。しばし、お茶などを沸かしてのんびりするが、小雨がパラついてきたので、あわてて荷物をまとめて石塚小屋に向かった。石塚小屋には宮野浦岳の頂上で顔をあわせた登山者が2名いるだけで、広々と使わせてもらうことができて楽しい夜を過ごすことができた。
|

|
|

|
|

|
|
石楠花に囲まれた鹿の沢小屋
|
|
永田岳の頂上直下には、こんな鎖場が!
|
|
宮の浦岳頂上で記念写真
|
|
|

|
|

|
|

|
|
宮の浦岳から先の稜線を行く。
|
|
投石(なげいし)湿原です。
|
|
花之江河に到着。
|
|
〈17日〉
今日は再び花之江河まで上り返し、湯泊歩道を下って、湯泊までの長い行動予定だ。
今日の朝も天気が悪く、カッパに身を包んでの出発になる。花之江河まで上がってきたところで少しガスが切れるが、栗生歩道の分岐を過ぎた辺りから再び雨が降り出す。ここから先は、昨日の登山道と違ってあまり整備されていない。沢が現れると丸太の橋を渡ることになるが、雨で滑りやすく、その度に緊張させられる。木々に覆われた道は展望も得られず、ひたすら歩く。
ワレノの岩屋で、雨を避けながら今日3回目の休憩をとる。4回目の休憩時に、足に山蛭が付いているのを発見する。沢のぼりで蛭には慣れているものの、いつ見ても気持ちの悪い生き物だ。ミノの小屋跡を過ぎて湯泊林道に近づくにつれ、足元に付く山蛭の数が増えていく。長い下りで疲れてきたが山蛭怖さにひたすら歩き、止れば足元の山蛭チェック。足に付いている山蛭は、虫除けスプレーをひと吹きすると簡単に落ちて、死んでしまう。立ち止まる度にシュッシュッの繰り返しだ。
ひょっこりという感じで、湯泊林道に飛び出す。幸いにも雨も上がったので、ここで登山を脱いで運動靴に履き替え、服の中に潜り込んでいる山蛭退治をする。あちこちに潜り込んでいるのを見つけては、シュッシュ・シュッシュ。30分かけて完全に退治して林道を下りはじめる。歩き始めた早々に、上がったと思った雨は再び降り始め、次第に雨足を増して、ついにはバケツをひっくり返したような豪雨となる。
林道は、道というより水路と化して、履き替えた運動靴は瞬く間に水浸し状態となってしまった。そんな雨も湯泊に着く頃にはすっかり上がり、無事に海浜温泉に到着する。
温泉から離れた海岸線の道の横にテントを張り、地元の店で買った食材でひとしきり宴会をし、暗くなってから温泉を楽しみ、そして寝ることにしたが、テントの中は蒸し暑くてサウナ状態で寝苦しい一夜となった。
|

|
|

|
|

|
小雨の中、石塚小屋を出発する。
|
|
花之江河を過ぎると、道は未整備で丸太橋が
多くなる。
|
|
雨の湯泊歩道を行く。
ガスと木々で、展望は得られない。
|
|

|
|

|
|

|
歩道横にあるワレノの岩屋で雨宿りをする。
|
|
蛭退治を終えて、湯泊林道を下る。
この後で豪雨となる。
|
|
湯泊海浜温泉を眺める海岸線にテントを張る。
|
〈18日〉
今日はバスで宮之浦に移動する。
これと言ってすることもなく、建設途中(?)の新港にある公園の東屋で濡れたものを乾かし、その合間に海水欲を楽しむ。この一瞬の時間のために水着をザックの中に入れて持ち歩いていただけに、「このチャンスを逃してなるものか」という感じだ。久しぶりの海水浴は、実に気持ちの良いものだった。
今夜も地元で買った食材で宴会をして寝る。暑いので、各人思い思いのところでゴロリと寝るが、夜半に雨が降り出してしまった。風に舞った雨粒が時折顔にかかり、その度に目が覚めて再び寝苦しい夜となってしまった。
|

|
|
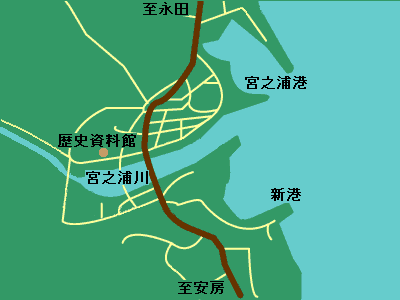
|
|

|
バスは「Food shop なかきはら」の前から出る。
|
|
屋久島最後の夜は、新港にある公園で寝ること
にした。
|
|
公園の近くで海水浴を楽しむ。
|
〈19日〉
今日は屋久島を離れる日だ。朝から何をするという予定も無いので、港の近くに移動して土産物を買い、食堂で屋久島最後の食事を食べる。フェリーに乗ったはいいが、出港直前に降り出した豪雨で甲板に溜まった雨で船が傾き、出港できない状態となる。最後まで屋久島らしさを見せてくれる。やがて雨も上がり、無事出航できたフェリーの甲板で最後の宴会をして帰ってきた。
|

|
|

|
|

|
出港時間になったが、突然振り出した雨で船が
傾き、しばらく天気待ち状態です。
|
|
船内では、またまた宴会です。
|
|
花火大会で人の多い、鹿児島港に到着
|
− 藤田 −
|


![]()
![]()