対局前
互先(たがいせん)の作法
対局者に棋力の差がなく対等の立場で行う対局です。
(1)碁盤の上に、碁笥を前後に置く。
(2)上座に年長者が着席する。
(3)ニギリで先手と後手を決め、コミ出しを確認する。
<ニギリの仕方>
・年長者が相手に個数が分からないように白石を握り、手を盤上に置く。
・年少者は黒石を1個(奇数)または2個(偶数)を盤上に置く。
・そのあと、年長者は握った白石が奇数か偶数か分かりやすいように2個ずつ盤上に並べる。
・年少者の置いた黒石数が、当たっていれば年少者が黒(先番)、当たらなかったら、
年少者が白(後番)となる。
(4)一礼して先手が黒、後手が白を持ち、碁笥を座席正面に
(テーブルの場合は右脇、左ききの時は左脇でも可)、碁笥の蓋は碁盤の右隅
(碁笥のあるときはその上方)に置く。
置き碁対局の作法
対局者に棋力の差がある場合、棋力の差を縮めるため、あらかじめ棋力差に応じた 個数の黒石を碁盤上において対局します。
(1)碁盤の上に、碁笥を前後に置く。
(2)上座に、上位者が着席する。
(3)一礼して上位者が白、下位者が黒を持ち、碁笥を座席正面に
(テーブルの場合は右脇、左ききの時は左脇でも可)、碁笥の蓋は碁盤の右隅
(碁笥のあるときはその上方)に置く。
(4)置き石の数と、コミ出しを確認する。
(級段位と置き碁 のページ参照)
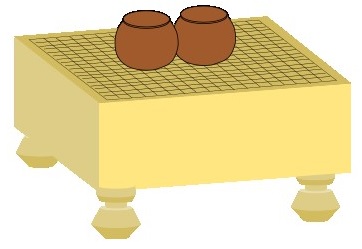
対局開始
先手が黒石、後手が白石を持ちます。
置き碁の場合、黒が置き碁を置きます。
1手目着手前にお互いが「お願いします」と挨拶します。
持ち時間
碁の勝負所、つまり考えるべき処で、しっかり考えることは大事で、
碁の上達や醍醐味でもあるが、
自己時間の配分ができるようしよう。
対局時計について
①対局時計の置き場所は白番の右側を原則とするが、決定は白番の権利です。
②石を置いた手で、対局時計のボタンを押すのがルールです。
(この習慣を身につけよう)
③終局時点で時計を止める。
④明らかな押し忘れや気づいていない残り時間の少なさを忠告してあげるのは、
自然な姿ですが、時と場合で、うるさいと受け止められることもあるので、注意を要します。
⑤相手の時間切れによる、逆転勝ちの策を労するのは、奨められません。